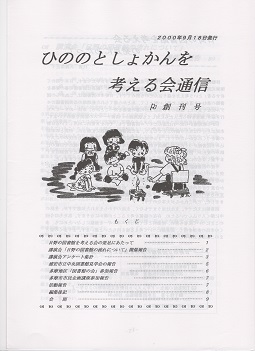
| 2000年9月18日発行 ▶PDF版創刊号 |
| もくじ 日野の図書館を考える会の発足にあたって 日野市立図書館の歩みを知るためのお薦め本 講演会「日野の図書館の流れについて」開催の報告 砂川雄一氏の主な論文・著作 講演会アンケート集計 浦安市立中央図書館見学会の報告 多摩地区「図書館の会」参加報告 多摩市市民企画講座参加報告 活動報告 会 則 編集後記 |
日野の図書館を考える会の発足にあたって
| 日野図書館は、35年前、日本で初めて開架式の図書館を作り、今日の公共図書館の基礎を作った先駆的な図書館です。地域に根ざした公共図書館は、図書館を利用する市民にさまざまな知識を提供する場です。図書館への関わり方は人さまざまでしょう。読みたい本を借りられる、知りたい情報をいち早く提供してくれる、知的要求を満たすための調査をする、子どもと一緒に楽しく児童書を選ぶなどなど、図書館は市民に開かれた自由な空間なのです。利用する年代に関係なく、障害の有る無しに関係なく、身近に民主主義の基本である市民が主人公であることを学べる場所です。 だが、行政の中に組み込まれている図書館は、行政の方向性に左右される危うさを持っています。市民が望むものと、行政が進めるものとの食い違いもでてきます。そのときは、図書館の持っている意義と必要性を認識し、市民の声を行政に反映させていくことが大切だと思います。「日野の図書館を考える会」は、2000年3月、市が提案した図書館条例の改定に市民が異議の声をあげ、条例をもとに戻すことができました。この事実を踏まえて、今後も市民と図書館が共同して、市民にとっての図書館のあるべき姿を模索していこうと作られた会です。 図書館を愛する多くの市民のご参加をお待ちしております。 (2001年3月版) |
| 移動図書館「ひまわり号」が日野市を巡回し始めてから35年たちます。日本で初めて開架式図書館が誕生したのです。また図書館設置条例の中に「館長は図書館司書の資格を有する者」という考え方を盛り込んだのも初めてです。日野市の図書館は、これからの図書館の進むべき道を示した新しい形として、あとから建てられた他地域の公共図書館のモデルになりました。職員の80%以上が司書の資格を持つことから、市民へのサービスも行き届き、障害を持った人たちに対しても肌理細かい情報サービスの提供を進めています。 しかし他地域から比べれば進んだモデル図書館でも、それを日常的に利用している日野市民にとっては当たり前のことでしょう。また図書館側も業務に忙殺され、市民との対話の場をつくれなかったのです。35年前の図書館設立当初は、どうしたら市民の中に入り込める図書館がつくれるか、職員も市民も必死で考えました。だが時代の流れや行政の仕組みの変化が、図書館に対する考え方を変化させ、図書館が地域の中で果たす役割はますます重くなるのに反して、35年の歳月は図書館設立時の理念を風化させてきました。 今度の図書館設置条例(館長の資格の変更)の一部改定の動きは、まさに市民と職員に突きつけられた図書館のあり方を問われる問題です。3月議会を前にして、私たちはわずかな日数の中で、改定をくい止めるため教育委員会に請願を出し、市長と話し合い、何とか合意できる内容(第5条2 図書館の館長は、図書館機能を達成するため、図書館法に定める専門的職員のほか館長として必要な学識経験を有する者とする。)を得ることができました。だがこれからが大事なのです。 図書館は文化です。文化は言うまでもなく、生活の中から生まれた知恵ですが、生活の中に深く入り込んでいるため、存在の価値を考えることが疎かになります。私たちは今回のことについて反省も含め、授業料として払ったエネルギーを無駄にしないためにも、多くの市民の参加を得て、図書館について考える場を持ちたいと思います。より多くの皆さまのご参加をお待ちしております。 (2000年6月版) |
日野市立図書館の歩みを知るためのお薦め本
| ☆『移動図書館ひまわり号』 初代館長前川恒雄著 筑摩書房 1988.04 ☆『図書館の誕生-ドキュメント日野市立図書館の20年-』 関千枝子著 日本図書館協会 1986.04 |
講演会「日野の図書館の流れについて」開催の報告
| 日時:2000年6月18日(日) PM2時~4時 場所:日野市中央福祉センター 講師:砂川雄一氏(第二代日野市立図書館長) 上記のように「日野の図書館を考える会」主催の講演会が開かれました。講演の内容は日野市立図書館の開館時から現在に至るまでの経過と、35年前、日野の図書館が掲げた新しい図書館サービスは全国の図書館に影響を与えたが、現在また図書館界は新たな問題を抱えていることなどを、元日野市立図書館長としての豊富な経験をお持ちの砂川氏らしい率直さで分かりやすく話されました。まとめとしては、行政は予算を「市民サービスの必要経費」と捉え、すべての市民の利用につながるものなので政策的経費として、大幅な予算削減には市長からの説明も必要。また将来構想は、現在のような困難な時にこそ市民参加を得て希望ある政策を考え、市民がスポンサーとして図書館に関わり、より高い要求を出していくことがこれからの図書館を考える上で重要であり、行政機関のひとつとして動いていては潰されてしまうと注意を喚起されました。前夜まで降っていた激しい雨も上がり大勢の市民が参加して講師のお話に熱心に耳を傾け、その講演会をきっかけに日野の図書館の歴史と今後の図書館の有り様を考えていくきっかけになればと思いました。 最後にこちらの不手際で2時間以上もお立ちになったまま、講演を続けられた砂川先生がお疲れではなかったかと反省し、お詫び申し上げます。 (文責 久保田) |
砂川雄一氏の主な論文・著作
| ☆『五つの公共図書館システム』 信田昭二・石橋幸男共著 日本図書館協会 1976.04 ☆『図書館は訴える-市民と読書-』 鈴木喜久一共著 岩波ブックレット 1986.05 ☆『日野市立図書館の現状と当面する諸問題について』 日野市立図書館 1995.11 ☆『東京における公立図書館施設の現状』 図書館研究三多摩 no.2 三多摩図書館研究所 1997.10 |
砂川雄一氏講演会アンケート集計
| 2000年6月18日 日野中央福祉センターにて開催 参加人数 41名 アンケート回収枚数12名分 (1)きょうの講演会はいかがでしたか。1つ選んでください。 良かった 9名(大変良かったと記した人 1名) 普通 3名 あまりよくなかった 0名 感 想 ・やはり歴史の渦中にあった人のお話は、迫力があるとおもいました。 ・ひと口に図書館といってもいろいろなのだということがよくわかりました。 ・輝かしい歴史と実績から、だんだんに離れていく今の実態の中で、再構築の時代だからこそ、強く信念をもって、広いビジョンで考えるのが大切であること、市民と一緒に、市民の力を借りて図書館を作っていくことを考えさせられた。 ・日野の図書館の歴史を再確認できた。図書館と市民との関係をもう一度考え直す機会となった。「資料提供」について考え直す機会になった。 ・砂川先生の生き様にも感動しました。大変良かったです。もっとまわりの友人に声をかければよかった。 ・砂川氏のお話がとても良かった。いろいろなことが知れて良かった。「専門職の看板を感じさせる職員ではいけない」とても重く大切な言葉ですね。 ・知らない部分を理解することができたように思います。 (2)この講演は何で知りましたか。(複数回答有り) ちらし 3名 広報 2名 友人・知人 7名 その他 3名(会からの手紙) (3)日頃、図書館を利用していて感じていることを自由にお書きください。 ・実用書が古い。(和洋裁・手芸・趣味・旅行等) ・二階の世界の都市地図をもう少し充実してほしい。 ・閉館時間が早く、平日に行くことができない。休日に予定が入ると図書館に行くことが難しくなる。遠いこともあって、利用したいのになかなかできないのが現状です。 ・日野市の図書館の問題は、こと日野市だけの問題ではなく、わが国の公共図書館界全体の問題です。 ・他市(地方)でも利用しますが、古いものから新しいもの固いものから軟らかいものと歴史でしょうか、置かれていることはよいことだと思いました。 ・ここ1年以上、忙しすぎて本を借りに行く暇がつくれなく、本を買うことも多かったが、お金が大変であった。夜間のサービス時間の延長を求めたいと思っている。 ・明るい雰囲気で気軽に利用できる点が良いと思う。 ・リクエストでほぼ目当てのものがそろうのですが、日にち等がかかる場合、必要な日に間に合わない場合がある。 (4)今後、この会に望むものがありましたらお書きください。 ・夏はクーラーのきく部屋にして欲しいです。今日は眠くなって困った。 ・そう大きな部屋ではありませんでしたが、講演者のことを考えると、マイクがあれば良かったと思います。 ・利用はしますが、図書館に関して知らぬことがおおいことに驚きです。いろんな分野で知らせて下さい。 ・働く者としては厳しいが、市民からの図書館評価を形にして出してみてもいいと思う。 ・市民と図書館職員がより高い理想、展望を計画し、その実現化に向けて一歩一歩前進していくための力になれたらすばらしいと思います。 ・利用者の図書館から見た図書館サービスの評価をし、反映できるような影響力を持っていただきたいと思います。 ・会則について。(例)街の人々が誰もが豊かに人間らしく生きる支えとなるような図書館づくりをめざす。 ・より幅広いメンバーで活躍できると良いと思います。現状の報告や利用している市民の率直な感想などとりあげてほしいです。 ・開かれたものになってほしい。身近に利用でき、サービスに徹していただきたいし、いろいろな分野のものがそろうことが嬉しく感じる図書館になるように思 います。  |
浦安市立中央図書館見学会の報告
| 8月2日(水)日野の図書館を考える会の会員9名が浦安市立中央図書館の見学にいってきました。 入口の右手には児童室があり、司書のおすすめの本が、表紙の見えるように書架やその上に並べられています。おはなしの部屋では司書による読み聞かせが行われています。 一般開架室は書架も低く、広い空間を感じさせます。本の配置は分類を崩し、利用しやすさに配慮され、OA関係は古い機種に関する本もそろえ、利用者から重宝がられています。 貸出窓口とは別に設けられた、『本の案内』は調べたいことがはっきりしない人も、ゆっくり相談にのってもらえる、カウンセリングコーナーです。利用者検索システムは、市のホームページにも入っているので、自宅のパソコンでも検索ができます。 図書館入口や廊下では「平和」「庭園」など、テーマをもった本の展示が行われています。 蔵書の豊富さと様々な工夫に、一同溜め息・・・。 ☆浦安市立中央図書館ミニデータ☆ 敷地面積 9,390.55㎡ 延床面積 5,185㎡ 収容能力 640,000冊 1階 一般開架室、レファレンス室、児童室、おはなしの部屋、点訳室、他面朗読室など 2階 視聴覚室(140席)、集会室、応接室、事務作業室など 地下1階 移動図書館倉庫、閉架式書庫など おはなし会 ストーリーテリング(語り) 毎週水曜日、毎月第4土曜日 絵本の読み聞かせ 毎週火~金曜日  全国一を誇る浦安市立図書館を支えているのは? どの自治体も財政難に悩んでいる中で、これだけの市立図書館を維持する秘訣はどこにあるのか、常世田図書館長に伺いました。「一番の基本は市民の支持です。」と館長。浦安市の図書館利用率は約60%、全国平均と比べても飛び抜けて高い数値です。これだけ多くの市民が利用する施設では、市もおろそかにはできない、ここがポイントです。 多くの市民に利用してもらうためには、いいサービスを提供することはもとより、講座や工作教室などを企画し、市民に図書館に来てもらう工夫をしています。(9月は週刊ダイヤモンド編集長の連続講座)市長や市議会議員の理解も大切、図書館利用者でつくる『友の会』からも積極的に働きかけてもらいます。市職員の仕事もしっかりサポートして、図書館の味方を増やします。とにかく、ありとあらゆる場を利用して働きかけていく日常の積み重ねが、全国一の図書館を支える秘訣のようです。 利用者がつくる図書館『友の会』 1992年のアメリカ図書館視察の際にふれた図書館友の会を参考に発足。登録会員は約70~80名、日常的に活動しているのは30名程度。非常勤職員で加入している人もいますが、基本的には利用者の会です。月1回「友の会デー」を開催、学習会やバザー、図書館長を囲む会、職員との懇談会などを企画しています。苦言を呈することもありますが、図書館の応援団として活動しています。市長や職員に働きかけるロビー活動も大切な活動です。 (清水記) |
多摩地区「図書館の会」参加報告
| 多摩の各市(小平・東久留米・東村山・田無・調布・多摩・保谷・八王子)の市民が図書館や文庫について考えようと自主的に集まり、情報交換や勉強会などを2ヶ月に1度小平市のルネ小平を会場に開いています。今回「日野の図書館を考える会」が発足したのをきっかけに、ぜひ参加してほしいというお誘いがあり、7月13日の午後初めて出席しました。私は日野の図書館の「条例改定」に伴う一連の報告をし、そのあと各市の情報や、図書館問題研究会の全国集会に参加された方の話を聞きました。助言者として出席されている学芸大学の山口源治郎先生が、今の図書館の置かれている状況分析や、委託・NPO方式による図書館の設置など、さまざまな事例を話されましたが、全国的に揺れ動いている図書館に対して、市民としてどう関わっていくのか考えさせられました。次回は9月21日(水)ですが、考える会の定例会で参加していくという承認を得ましたので引き続き報告していきます。 参加者 久保田 (久保田記) |
多摩市市民企画講座参加報告
| ☆6月25日PM2時~4時30分多摩市公民館ベルプ永山に於いて、多摩市に中央図書館をつくる会主催の講座に参加。講師は浦安市立図書館長常世田良氏。参加者 山口・久保田 ☆7月15日(土)PM2時~4時 多摩市関戸公民館集会室 テーマ 「生涯学習と公共図書館」 講師:塩見昇氏大阪教育大教授) 参加者:宮田 |
活動報告
会則
編集後記
| ☆寝耳に水のような出来事から早7ヶ月余り。 創刊号をだすにあたって振り返ってみると、何とも盛りだくさん!怒りのパワーは団結力もとても大きいものだと実感!このエネルギーをこれからは、よりよい図書館づくりのために、みんなの力を穏やかに、心豊かに、途切れる事なく注いでほしい。 (K.M) ☆創刊号を意識しすぎたのかちょっぴりかためなメニューになってしまいました。反省。 (H.I) ☆この通信は点訳版もあります。ご希望の方は事務局までお申し出下さい。 |
【記録】ひののとしょかんを考える会通信 創刊号
